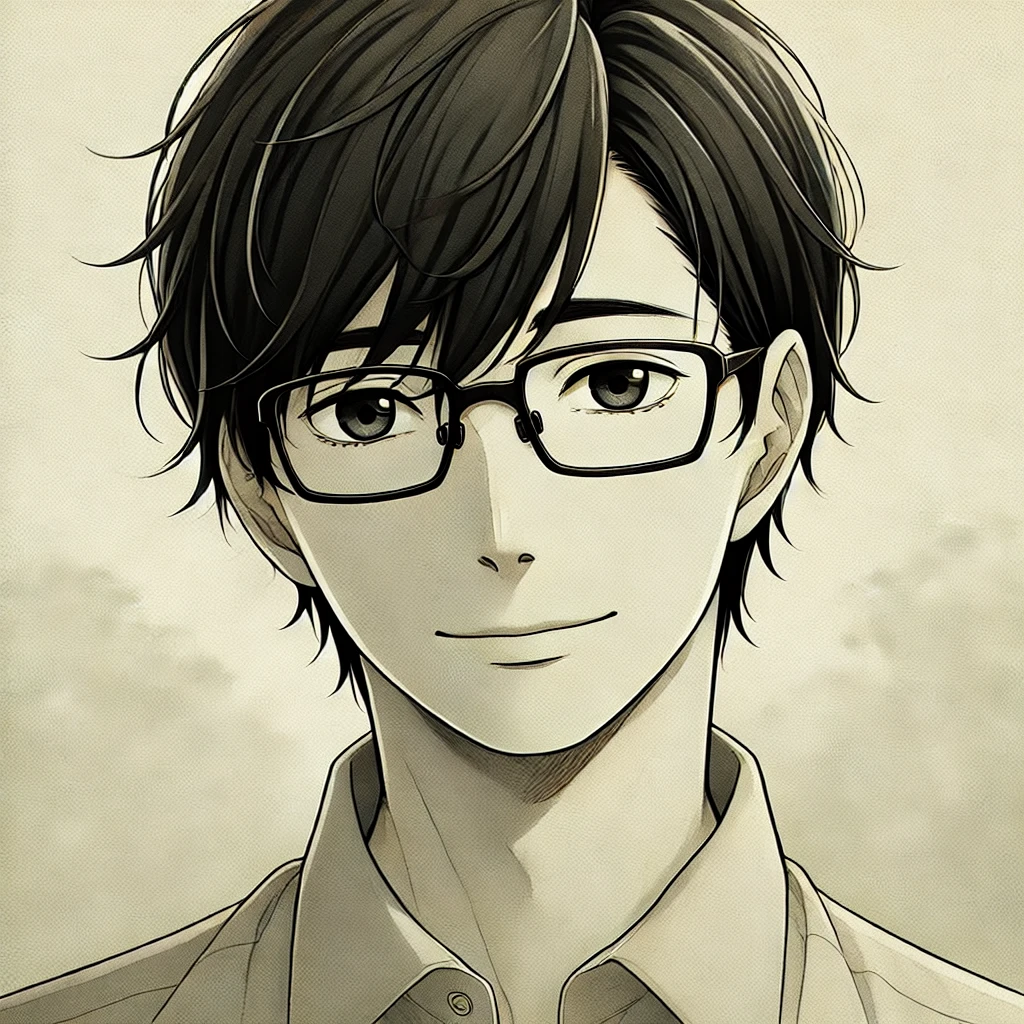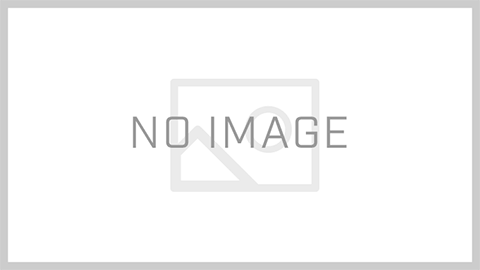私たちは日々、ニュースやSNS、書籍、仕事などを通じて、さまざまな情報に触れています。
昔は、図書館で調べたり人に聞いたりと、情報を得るだけでも手間がかかりました。
今ではスマホひとつで、AIに聞けば欲しい情報が瞬時に手に入る時代です。
一方で、誰でも情報が手に入れられるようになった今では、情報そのものの価値はかつてほど高くありません。
まるで、水道水に特別な価値を感じないように、情報も「ありふれた存在」になりつつあります。
だからこそ、今求められているのは「情報の組み合わせ方」です。
「どのように組み合わせ、どのような視点で活かすか」という発想力が、これからの時代には求められるでしょう。
今回は、そんな発想力を高めるための「3つの工夫」とアイデアが生まれやすくなる実践的なヒントをご紹介します。
アイデアは情報の掛け算
「アイデア」と聞くと、「突然ひらめく何か」のようなイメージを持つ人も多いでしょう。
しかし実際には、前提となる「素材」がなければ、アイデアは生まれません。
たとえば、今なお生み出される物語の多くも、さまざまな「元ネタ」が複雑に組み合わさってできています。
一見全く新しいように見える物語も、構成を分解してみれば、既存の物語とよく似た展開や構造を持っていることが少なくありません。
実際、物語には「シンデレラ曲線」「起承転結」「序破急」などの型があり、そこを土台として経験や知識を掛け合わせることで完成となります。
このように、既存の情報をどのように組み合わせるか――それこそが「発想力」であり、アイデアの本質なのです。
発想力の土台は日々のインプット
アイデアは既存の情報を組み合わせて生まれるため、質の高いインプットが欠かせません。
仮に、情報のインプットの習慣がないのであれば、アイデアの前にインプットをする習慣をつけることから始めましょう。
- 学ぶこと
YouTubeやインターネットで情報を得ることも有効ですが、おすすめは読書です。本はネットの情報と比べて情報の精度が高いからです。もし、どの本を読めばよいかわからない場合は、AIに判断を委ねてみるのも有効です。 - 体験(経験)すること
五感を通じた体験もまた、重要な情報源です。新しい体験は、新たな発見や視点をもたらし、アイデアにつなげてくれます。
インプット方法は、大きく分けて上記の2つに分類されます。
これらを通じて「記憶もしくは記録すること」が重要です。
人は一度に多くの情報を処理しきれず、「重要と思った部分のみを記憶する性質」があります。
覚えきれなかった情報を見返せるように、メモやボイスレコーダーなどで記録するなどの工夫も大切です。
■AIを使いこなせたらインプットは不要?
インターネットの普及以降、「情報は必要なときに調べればいい」という考え方が広がってきました。
さらに近年では、AIの進化によって、「調べる」という行為すら不要になるかもしれません。
このような流れを受けて、「もはや学ぶ必要はないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
確かに、AIを活用すれば、指示を出すだけでプロ顔負けのアウトプットが得られることもあります。
しかし、それでも「学ばなくてよい」とは言い切れません。
理由は主に2つあります。
①AIが正しいとは限らない、情報の判断は依然として人に求められる
AIは非常に優秀ですが、間違った解釈で回答したり、詳しくなければ気づかないような細かな間違いも見受けられました。
こうしたミスを見抜くには、ユーザー自身が基礎的な知識や情報の信頼性を見極める力を持っていることが前提です。
②同じAIを使っても、結果に差が出るのは「使い手の発想力」
特に、意図した回答を得るための「質問力」、複数の情報をつなぎ合わせて意味を生み出す「発想力」は、使い手に大きく左右されます。
AIは膨大な情報を持っていますが、それを活かせるかは使い手次第です。
全てをAIに任せきりにするのではなく、あなたも学ぶことや考えることが求められます。
アイデアを引き出す3つの工夫
ここからは、あなたが持つアイデア力を最大限引き出すための工夫をお伝えします。
✅記録をあえて未完成にしておく
✅空白を活用する
✅適切な質問を投げかける
記録をあえて未完成にしておく
記録をするとき、一字一句丁寧に書いていませんか?
アイデアを出すためには、
- あえてキーワードだけ抜き出して書く
- 学んだ内容に関連した情報を1つ加えてみる
空白を活用する
一見何も考えていないと思うような場面でも、脳は思考を巡らせています。
もしアイデアを出したいのであれば、「時間の空白」をうまく活用しましょう。
下記のような方法を用いることで、「時間の空白」をうまく活用できます。
①ノートやメモに意図的に空白を設ける
あらかじめ、ノートの半分や一行ごとに空白を設ける方法です。
定期的にノートを見るようにして、浮かんだ内容を空白部分に記入していきます。
疑問を書き加えるなどの工夫をすると、質問に応じたアイデアが浮かびやすくなるので、オススメです。
②時間の空白を意図的に設ける
お風呂に入っていたら、突然アイデアが浮かんだ経験はありませんか?
「ボーッとする時間」を意識して作ってみましょう。
アイデアは浮かんだらすぐに消えることもあるので、メモなどを用意しておくと良いでしょう。
③適切な質問を投げかける
質問を投げかけることで、脳は自然とその答えを探し出そうとするので、その過程でアイデアが生まれることがあります。
「アイデアが浮かばないときに投げかける質問」を決めておきましょう。
5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)を意識して自分に合った質問を考えてみましょう。
以下に一例を挙げておきますね。
- もし正解を持っていなかったとして、どこに答えがあるだろう?
- もしこの案の他に良い案があるとすれば、何だろうか?
- もし○○さんだったら、どう考えるだろう?
上記のように、「結論にとどまらない問いを自分に投げかけること」がポイントです。
■アイデア出しに活用している2つのアイテム
「アイデアが浮かばない」と思ったときに、意図して使っている2つのアイテムを紹介します。
①アイデアを広げたいことを紙に書き出す
時間をかけて悩んでいたことでも、視点やタイミングを変えるだけでアイデアがたくさん出ることもあります。
とっさに浮かばないときは、とりあえず紙にメモをして、そのまま時間を空けることを心がけています。
②マインドマップで情報を掛け合わせる
マインドマップは、中心にテーマを書き、そこから関連する情報を放射線状に広げる発想ツールです。
1つのキーワードから、連想を膨らませる過程で新しい発見や意外な組み合わせを見つけたりできます。
まとめ
今回は、アイデアを出すためのインプット方法とその活用方法について紹介しました。
- アイデアは既存の情報の組み合わせであるため、質の高い情報を記憶or記録することが大切
- アイデアを引き出す工夫①:記録をあえて未完成にしておく
- アイデアを引き出す工夫②:空白を活用する(時間やノートの空白)
- アイデアを引き出す工夫③:適切な質問を投げかける
✅メモやノートをあえて未完成に残しておく
✅時間・ノートに空白を作り、そのスペースを使って思考を巡らせる
✅「なぜ?」「ほかに案は?」など、自問を活用してみる
情報入手が困難な時代においても発想力は大切でした。
発想力を鍛えて変化の大きい時代を生き抜きましょう。