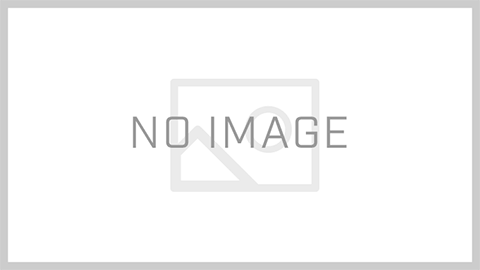AIや科学技術の進化により、私たちの働き方や求められるスキルが大きく変わりつつあります。
日常的な業務や単純作業は次々と自動化されている時代の流れに対して、「今までのやり方ではうまくいかないのではないか」といった漠然とした不安を感じていませんか?
その原因のほとんどは、「自分の強み」を明確に把握できていない点にあります。
この記事では、「これからの時代に必要な強みの見つけ方」と「代替不可能なスキルを磨き続けるための戦略」についてお伝えします。
この機会に、「あなたの得意」について深く考えてみてはいかがでしょうか。
自分の強みを特定する2ステップ
①強みの特徴からあなたの強みを考える
- 他人より簡単にできること
- 他人に褒められること
- 他人に頼られることが多いこと
- 自然と没頭できること
- 過去にうまくいったこと
この5つの特徴は「あなたの強み」である可能性がありますので、以下のように自問しながら思い浮かんだことを紙に書き出してみましょう。
- 他の人が苦労しているのに、自分はすんなりとできることは何?
- 周りの人からよく褒められることは何?また、どういう場面で褒められることが多い?
- 誰かに頼られることが多い作業や仕事は何?また、その理由は何だと思う?
- 自分が自然と没頭できる活動や仕事は何?
- 特に苦労せずにうまくいった経験は何?
「本当にこれが私の得意なことなの?」と疑問を抱くことでも「経験不足」が原因かもしれませんので、可能な限りチャレンジしてみることをオススメします。
②自己分析ツールを使って客観的に特定する
戦略①:16パーソナリティ診断(MBTI診断)を活用する
16パーソナリティ診断は、MBTI(性格タイプ指標)をもとにした自己分析ツールで、昨今は「キャリア支援」の観点から注目されている診断方法です。
人の性格を16種類に分類しており、質問に答えるだけで自分の特性を知ることができます。
【参考】
戦略②:AIを活用する
ChatGPTをはじめとしたAIを活用してみましょう。
たとえば、以下のように目的を明確にして質問することで、より具体的な回答が得られやすくなります。(実際にChatGPTに添削してもらっています)
- 自分の強みを仕事でどう活かすか悩んでいます。自分の強みを見つけるヒントが知りたいです。
- 自分の強みを把握できていない気がします。見つけるためのアドバイスを教えてください。
■占い本を活用してみる
この戦略は、「占いに抵抗がない方向け」限定の方法です。
占いと聞くと、少し怪しいと感じる方もいるかもしれませんが、実際には誕生日などを基にした統計学的な要素が含まれています。
以前、占い本に「これって自分だ」と感じるような特徴がいくつも書かれており、驚いた記憶があります。
過度な信頼は禁物ですが、「当たっている」という声が多い占い本なら何でも構わないので、強みを見つける参考ツールとして活用してみてください。
強みを磨くために必要な3つのポイント
ここからは、強みを磨くために心がけたいことについて、3つほどお伝えします。
1.強みを活かすためる「学びの時間」を設ける
もし、1つでも見つかったのであれば、自己投資に使える時間を「あなたの得意なこと」に費やしてみましょう。
得意なことを磨くためには、「学びを継続すること」が前提です。
冒頭にも触れたように、テクノロジーの進歩により、AIなどの新しい技術が生まれており、私たちに求められている役割は日々変化しています。
2000年以前と比べて、私たちが持つべきスキルの重要性は大きく変わりました。
単一のスキルを磨き上げずともキャリアを築ける時代だったのに対して、現在はAIと差別化できることが求められています。
人間にしかできない「創造性」や「感情表現」を絡めることも必要になってきており、スキルはそれらを「活かすための土台」程度の重要度となっています。
そのため、かつて得意だったことが役に立たなくなったり、新たな強みがまだ見つかっていないこともあるでしょう。
だからこそ、自分の得意なことが何なのかを深く考え磨き続けることで、他者に代替されにくい「あなた」というブランドを創る必要があります。
2. SMART目標を設定して具体的な計画を立てる
得意なことを磨くための「行動目標を明確にすること」でより洗練することができます。
明確な行動目標を立てるのに「SMARTの法則」をぜひ活用してください。
フォーブス(Forbes)の調査(The Power of SMART Goals: 30% more likely to succeed.)では、SMART目標を採用したグループは、漠然とした目標のグループに比べて、成果が約30%向上すると述べられています。
以下の条件を満たすように、行動目標を設定してみましょう。
- より具体的になるように(Specific)
- 測定ができるように(Measurable)
- 達成ができる範囲内で(Achievable)
- 目標と関連性がある(Relevant)
- 期限が設定されている(Time-bound)
「1年以内に英語力を上げたい」場合のSMART目標の例
⇒「毎週30分の英会話レッスンを受け(Measurable:測定可能)、6か月後に(Time-bound:期限)TOEICで700点(Achievable:達成可能)を目指す」
(全体的に《Specific:具体的》と《Relevant:関連性》も満たしている)
無理せず、焦らずに磨き続ける
得意なことを磨くことは、ほんの数か月程度で完璧に仕上げるようなテーマではなく、今後の人生を通じて取り組むテーマです。
短期間での成果に一喜一憂するのではなく、長期的に成長できる仕組みを作ることが重要です。
特に、初めのうちは無理せずに「決めた行動を継続することだけ」を意識ながら行動してみましょう。
このときに、「10分程度でも達成できるような『小さな目標』を立ててから行動すること」を心がけてみてください。
自己啓発本などでよく見る、いわゆる「スモールゴール」という手法です。
小さな目標達成を繰り返すことで「心理的な達成感」を得られ、その結果行動を定着させやすくなることが、様々な行動経済学の研究で明らかになっています。
前述した「SMART」の手法も併せて活用することがオススメです。
【参考記事:スモールゴール】
スモールゴールの活用法:初心者が目標を達成するための3つのコツ
3. 振り返りと改善のサイクルを作る
自分の強みを磨くには、行動の振り返りも必要です。
うまくいった場合
- 今回の取り組みでうまくいったところは何?
- うまくいった理由は何?
うまくいかなかった場合
- 今回の取り組みでうまくいかなかったところは何?
- うまくいかなかった理由は何?
- 何か改善できることはある?
上記のような自問を用いて次回以降の行動の改善点を定期的に探っていきましょう。
時には他者からのフィードバック(同僚や上司など)をもらうことも良いですし、最新のテクノロジー(AIなど)を活用して次回以降の行動のヒントをもらうのも良いでしょう。
普段他者からのフィードバックを積極的にもらわない人ほど、新たな気づきを得るきっかけとなるでしょう。
ちなみに、フィードバックを定期的に活用した人は、そうでない人に比べて自己改善率が25%高まることがコロンビア大学の研究で示されています。
同じ行動時間でも、改善の有無で成果が大きく変わってしまいますので、思い至ったときに振り返ってみると良いでしょう。
失敗から学ぶことの重要性
失敗から目をそらしたくなるのも理解はできますが、ぜひそこからの学びをもとに改善をすることを心がけましょう。
「成功につながる貴重な経験」につなげることもできるようになります。
ハーバード大学の研究によると、学習における失敗は成功よりも脳に強い印象を残し、記憶と学習の定着に貢献することがわかっています。
「同じ失敗をしないように」と意識しているからか、失敗したことって結構覚えていたりするものですよね。
一度の失敗で自分を評価するのではなく、それをどう活かすかが真の評価につながります。
ちなみに、多くの成功者やリーダーと呼ばれる人たちは、失敗を経験することで新たな視点や洞察を得て、自分を磨いています。
例えば、Googleの元CEOエリック・シュミットは、失敗を繰り返し試行錯誤することが、最終的なイノベーションにつながると語っています。
行動に失敗はつきものですが、それを恐れるのではなく「学びの機会」として捉えることが、何より大事なことです。
まとめ:自分の強みを見つけて磨く方法
- 自分の得意なことを見つけるために、5つの質問を通じて自己分析を行う
- SMART目標を設定し、具体的かつ測定可能なプランを立てることで、効率的に得意なことを磨く
- 得意なことを学び続ける姿勢を持ち、磨きをかける
- フィードバックを活用し、他者からの意見やAIなどのテクノロジーを活かしながら行動を改善し続ける
- 失敗から学ぶことを恐れず、それを成長の糧として長期的な成長へつなげる
これからの時代において、あなたの得意を磨き続けることが不可欠です。
重要なのは、他者との比較ではなく、自分自身の成長に焦点を当てることです。
時間をかけて、自己の可能性を最大限に引き出し、最終的には自分が思い描く未来へと進んでいくことでしょう。
まずは、「得意なことを見つけるための5つのヒント」を参考にしながら、あなたの得意なことを明確にするところから始めてみてはいかがでしょうか?


-640x360.jpg)